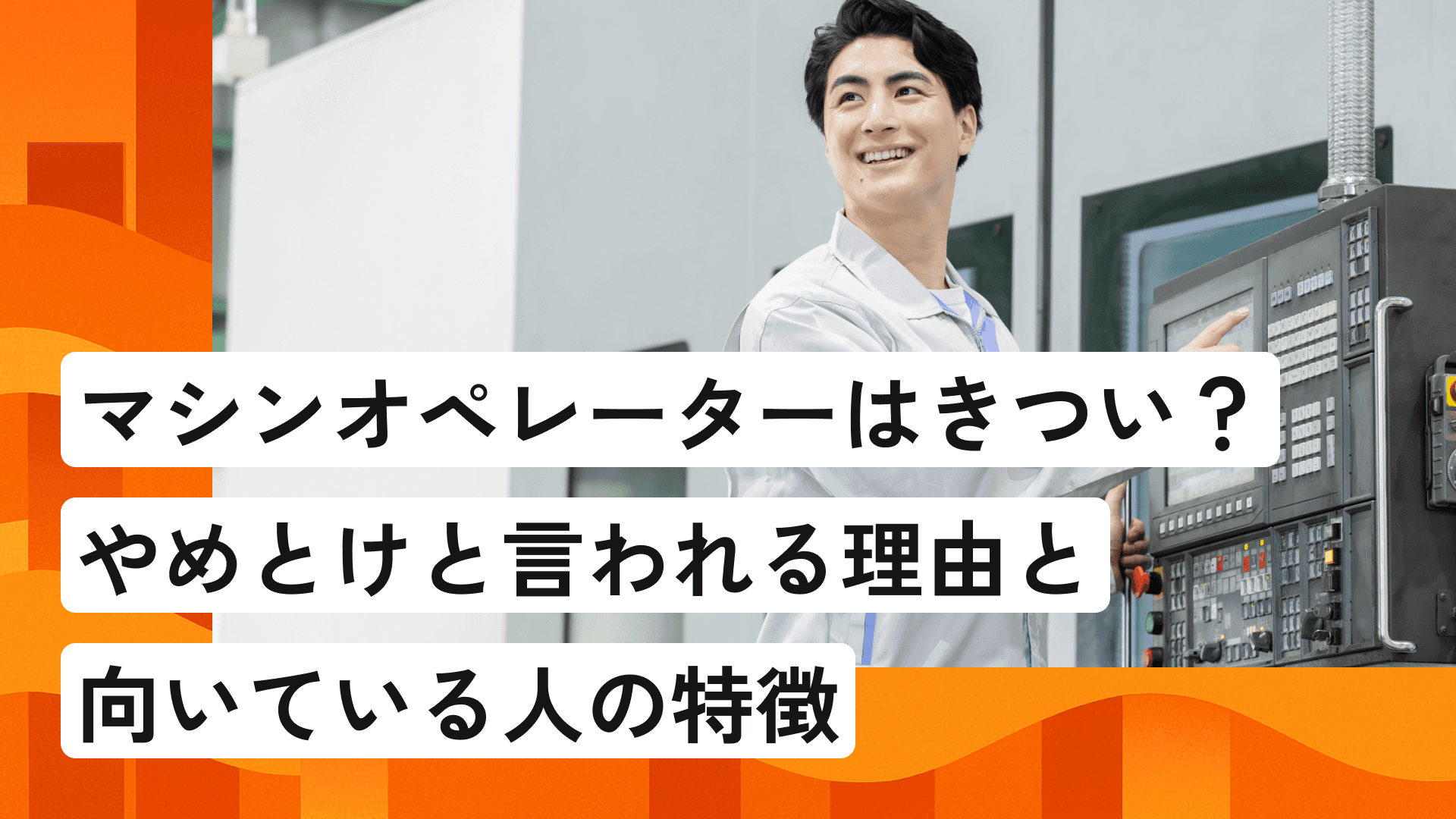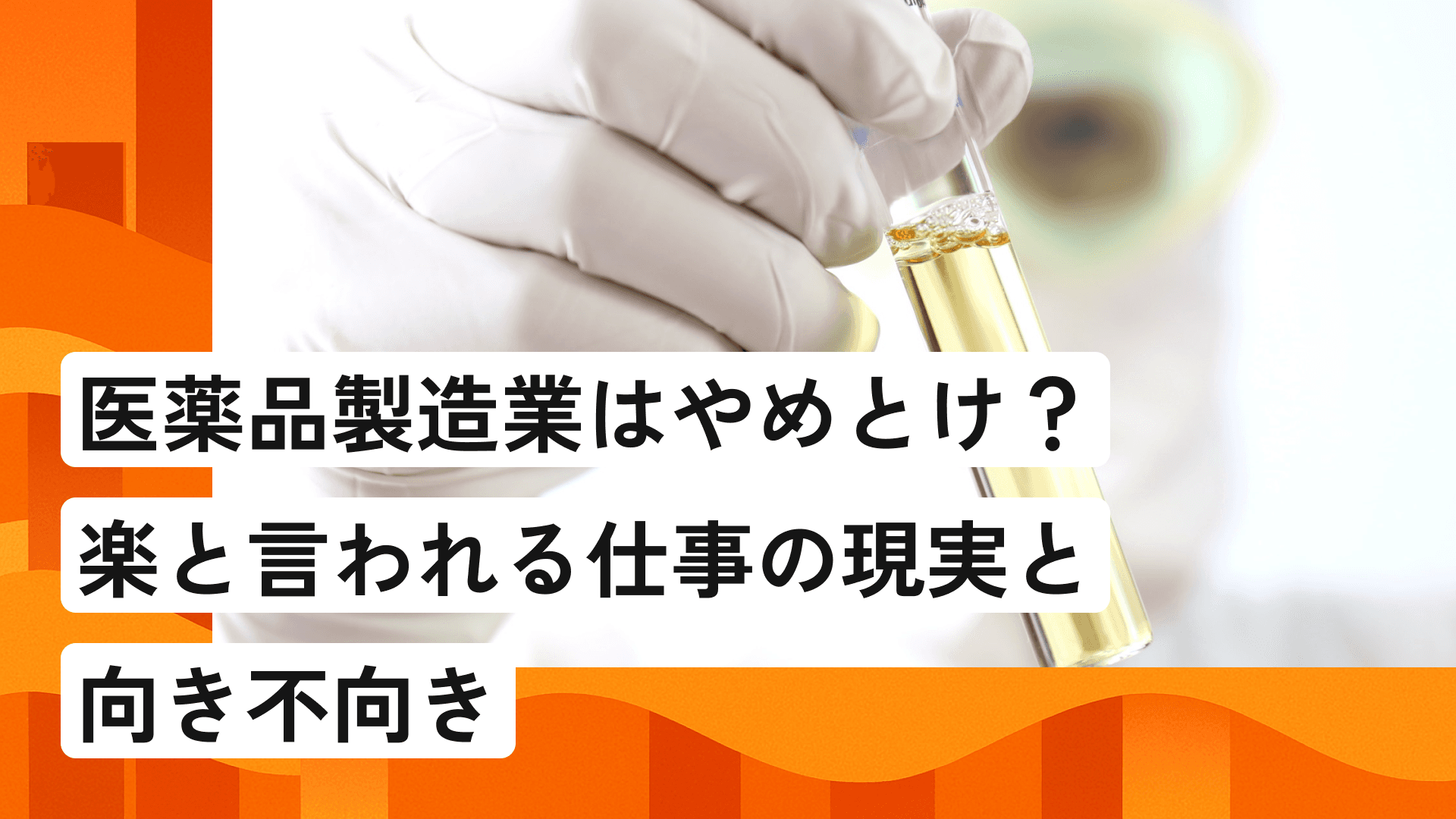メーカーや製造業は一見すると同じように思いますが、実際にはどのような違いがあるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。扱っている製品や取引先によってどちらに該当するかも異なります。本記事では、製造業とメーカーの違いや職種、メリットやデメリットについて紹介します。また、製造業やメーカー勤務に向いている人についても解説します。
製造業とメーカーの違い
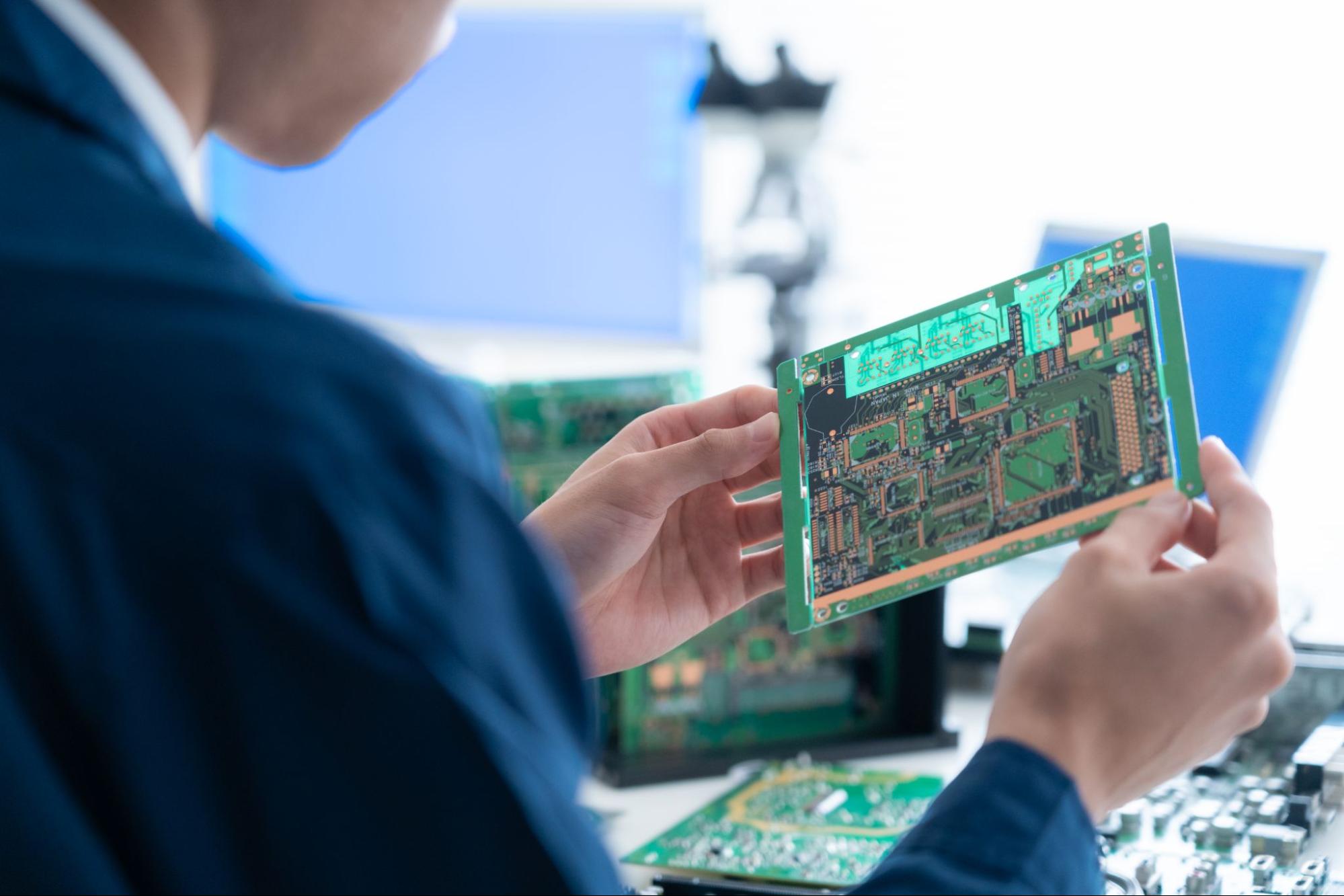
製造業とメーカーは、厳密にはそれぞれ異なる定義を持っています。ここでは、製造業とメーカーの違いについて企業規模と製造している製品の2点から解説します。
企業規模
製造業の場合、製品に使われている部品の一部の製造を担う企業など産業全体を指し、従業員数も数人〜数十人程度と規模も小さい傾向にあります。一方でメーカーは、資材の調達や製品の開発、生産などを一社で行う点が特徴です。そのため、必然的に企業規模も大きくなります。
製造している製品の違い
以下の表の通り、製造業とメーカーでは扱っている製品が異なります。メーカーでは消費者や企業向けの製品を製造している一方、製造業では企業向けの製品を取り扱っているといった特徴があります。
メーカー | 製造業 | |
製品の特徴 | 素材や部品などを生産しているほか、自社製品の製造を行っている | 自動車や住宅に使用される部品などを製造 |
ビジネスモデル | 消費者や企業向けの製品を提供 | 主に企業向けの製品を提供 |
メーカーの種類

製造業と混同しやすいメーカーですが、主に以下の3つに分類されます。
- 素材メーカー
- 部品メーカー
- 加工メーカー
ここでは、上記の各メーカーがどのような役割を持っているかについて解説します。
素材メーカー
素材メーカーは、製品に用いられる素材を生産するメーカーで、製品作りに不可欠な役割を担っています。基本的に企業向けに素材を提供しており、鉄やガラス、紙、金属など種類も様々です。素材の質によって製品の仕上がりも変わるため、研究開発しながら質の高い素材を提供しています。
部品メーカー
部品メーカーは、素材メーカーが生産した素材を使用して製品に必要な部品を生産している点が特徴です。自動車や家電、スマートフォンなど日常生活に必要な部品を製造しており、日本だけでなく海外とも取引を行っています。素材メーカー同様、取引先は製品を取り扱っているメーカーがメインとなっています。
加工メーカー
加工メーカーは、部品メーカーが製造した部品を用いて製品を作るメーカーです。自動車や家電メーカーは外注先で製造した部品を組み立てるケースが多いですが、化粧品や薬品を取り扱っているメーカーの場合、自社で素材の生産から製品の加工までを担当しています。
製造業の種類

製造業の場合は、主に以下のように分類されます。
- 食品
- 自動車
- 住宅
- 半導体
- 金属・鉄鋼
ここでは、上記の各分野の特徴について解説します。
食品
食品関係では、乳製品やお菓子、ジュース、大豆加工食品など様々な食品や飲料の製造を行っています。生産に必要な原料の調達や加工、出荷などを自社で行っているケースが多く、小売店や飲食店などが主な取引先です。手作業で生産しているケースもありますが、近年はすべての工程を自動化しているケースも珍しくありません。
自動車
自動車は、エンジンやタイヤ、ボディなどの製造を行っており、塗装や溶接、組み立てといったように製造工程も細かく分けられています。ライン作業にて自動車の製造が行われ、完成した自動車は検査部門でチェックされた上で出荷されます。
住宅
住宅に関連する製造業の仕事は、ドアや窓、外壁など家屋を建てる際に必要な設備の製造など幅広いものがあります。設備のほとんどを工場で生産するケースが多く、中には部屋そのものを製造する企業も存在します。現在はリフォームの需要も増えているほか、地震などの災害に強い住宅に対するニーズも増えています。
半導体
パソコンやスマートフォン、タブレットなどの電子機器に欠かせないものとして半導体がありますが、半導体の製造も世界規模で広がりを見せています。日本でも国内企業が半導体の製造に携わっているほか、海外企業が日本に生産拠点を設けるといった動きもあります。日本は世界的にも半導体のシェアが大きく、今後も自動車や住宅など様々な分野での需要拡大が期待されるでしょう。
金属・鉄鋼
金属や鉄鋼は自動車のボディや家電の部品、建築物など様々な製品に使われており、現在は鉄やアルミ、銅などのスクラップを活用して新たな製品を生み出す仕事も行われています。主な仕事内容は、くず鉄などを溶かして建物などに使用される鋼材や、航空機のエンジンやベアリングに用いられる鋼材の製造を行っています。
製造業やメーカーの職種

製造業やメーカーは工場での仕事だけではなく、営業や設計、生産管理など多岐にわたります。ここでは、製造業やメーカーにはどのような職種があるのかについて解説します。
営業
営業は、自社製品を販売してくれる小売店や購入してくれる企業などに対して行われます。企業に対して営業活動を行う場合、新規顧客の獲得を目指す「新規営業」や、既存顧客に新製品を紹介する「ルート営業」に分類されます。消費者に直接営業活動を行うケースは少なく、企業が主なターゲットです。
研究・商品開発
研究は、新製品の開発や既存製品の改良、製品に使用する素材の研究などを行います。商品開発は市場やトレンドの調査、自社製品を利用している顧客のデータ分析などを行い、商品開発に向けたアイデアの構築などを担当している点が特徴です。専門的な知識が求められるほか、他部門と連携して業務を進めていくケースが多いです。
設計
設計は、ニーズに合った製品を作るために設計図を作成する仕事で「構想設計」や「基本設計」「詳細設計」といったように細かく分けられています。製品の基本的な設計や仕様を設計図に落とし込み、その後製造できる段階まで詳細を詰めていく流れとなります。
製造
製造は、できあがった設計図をもとに製品を作る部門です。設計図通りに製品ができあがるか技術が問われる職種であり、仕上がりに問題がある場合は問題点を分析した上で改善しなければなりません。また、製品だけでなく生産ラインの見直しなどが求められる場合もあります。
生産管理
生産管理では、計画通りに製品を作るための計画の作成や、製品の品質管理を行います。生産数が毎日のように変動する場合は、最適な生産スケジュールで稼働できるように関係者とすり合わせをする必要があります。
資材調達
資材調達は、製品の製造に必要な素材の買い付けなどを行い、国内だけでなく海外の企業とも取引を行うケースがあります。できるだけコストを抑えるために取引先と交渉を行うほか、企業独自の調達ルートを開拓することも資材調達の仕事の一つです。
設備保全
設備保全は、生産ラインが問題なく稼働できるよう、点検やメンテナンスなどを担当する職種です。突発的なトラブルが発生した際は迅速な復旧が求められるほか、部品の調達なども担当します。
大手メーカーと中小製造業のどちらに就職・転職すべき?

大手メーカーでの仕事は、流れ作業や同じ作業を繰り返すなど集中力が求められる作業が多い傾向にあります。一方で、中小製造業の場合は、製品や担当する作業に対する知識やノウハウが求められることも多くあります。このことから、単純作業が苦ではない人は大手メーカーを、積極的にスキルアップを図って仕事をしたい人は中小製造業を選ぶと良いでしょう。また、福利厚生や給与面も大手メーカーと中小製造業では異なるため、業務内容以外の部分でもどちらを選ぶか検討してみましょう。
メーカーや製造業の将来性は?

少子高齢化による人手不足の深刻化やAIの導入などにより、メーカーや製造業における状況は大きく変化しています。しかし、すべてのメーカーや製造業が将来性に不安があるわけではありません。例えば、半導体分野の場合、政府が半導体を生産する企業の合計売上高を2030年までに約15兆円以上にすることを目標とし、海外半導体メーカーの製造拠点を日本に設置する際に支援を検討しているといった動きがあります。このような取り組みを通じて、国内の雇用増加や製造業の需要拡大が期待できるでしょう。
メーカーや製造業で働くメリット

メーカーや製造業で働く上で得られるメリットには、以下のようなものがあります。
- 未経験の人でも働きやすい
- 社会に貢献している実感を得やすい
- 雇用が安定している
- スキルアップやキャリアアップが見込める
ここでは、上記のメリットについて解説します。
未経験の人でも働きやすい
メーカーや製造業は作業工程がマニュアル化されているケースが多いです。そのため、未経験で専門知識を持っていなくても働ける体制が整えられています。業務に必要な知識も働きながら身につけられるので、未経験の人でも安心して働けるでしょう。
社会に貢献している実感を得やすい
メーカーで働く場合、日常生活で使用されている製品の製造に携わることができます。スーパーやホームセンターなどで見かける製品を開発する部署や生産ラインに配属されると、自分が関わった製品が社会に貢献していると実感しながら作業できるでしょう。
雇用が安定している
製造業やメーカーに勤務すると、原則として長期雇用が前提となるため、安定した仕事に就きたい人に適していると言えます。また、有給休暇や住宅手当、交通手当などの福利厚生が充実しているなど、従業員が長期間働ける環境が整っています。
スキルアップやキャリアアップが見込める
メーカーや製造業問わず、仕事を通してスキルアップやキャリアアップが見込める点もメリットの1つです。一連の製造工程に関する知識や機械の操作だけでなく、問題解決能力やコミュニケーション能力などのビジネススキルを習得することで、人事からの評価が得られキャリアアップが見込めます。
メーカーや製造業で働くデメリット

メーカーや製造業で働くと、雇用の安定や社会貢献への実感などさまざまなメリットを得られますが、一方でデメリットもいくつかあります。ここでは、主なデメリットを3つ紹介します。
転勤が発生することがある
大手メーカーの場合、全国各地に工場を設けているケースがあるため転勤が発生することもあります。また、中小企業でも転勤の可能性があり、状況によっては突然異動を命じられる可能性も否定できません。転勤を避けたい場合は、できるだけ規模が小さい企業への就職や転職を目指すと良いでしょう。
年功序列の風潮が残っている企業もある
現在は年齢を問わず成果を出している人が出世しやすい傾向にありますが、年功序列の風潮が残っている企業もあります。企業の歴史が長く経営が安定している企業であるほど、勤務年数などで昇進を判断することが多いです。そのため、実力で出世を狙いたい人には厳しい環境に感じられるでしょう。
他業種でも役立つスキルの習得が難しい
メーカーや製造業での仕事は企業独自のスキルや知識を習得することが多く、他業種に活かしにくいといった点があります。そのため、転職を検討しても希望する業種や職種が限られてしまい、同じような企業を選ばざるを得ないといったことも考えられます。
メーカーや製造業での仕事に向いている人

メーカーや製造業の仕事に向いている人には、以下のような特徴があります。
- 責任を持って仕事ができる人
- ものづくりに興味がある人
ここでは、上記の特徴について解説しますので、自分が当てはまるか見てみましょう。
責任を持って仕事ができる人
メーカーや製造業で働く場合、納期を守ることはもちろん決められた品質に収まるよう製品を作ることが求められます。そのため、製品が出来上がるまで責任を持てる人が向いていると言えるでしょう。品質に問題のある製品を作ってしまうと、取引先からの信頼を失いかねません。信頼を落とさないためにも、一定の品質を維持しながら製造に携われる人が求められます。
ものづくりに興味がある人
ものづくりに興味がある人も、メーカーや製造業に向いていると言えます。製品が完成するまでには設計や開発、製造などさまざまな過程を経ており、この過程で得られる知識やノウハウを積極的に習得できる人はメーカーや製造業で十分活躍できるでしょう。
メーカーや製造業での仕事に向いていない人
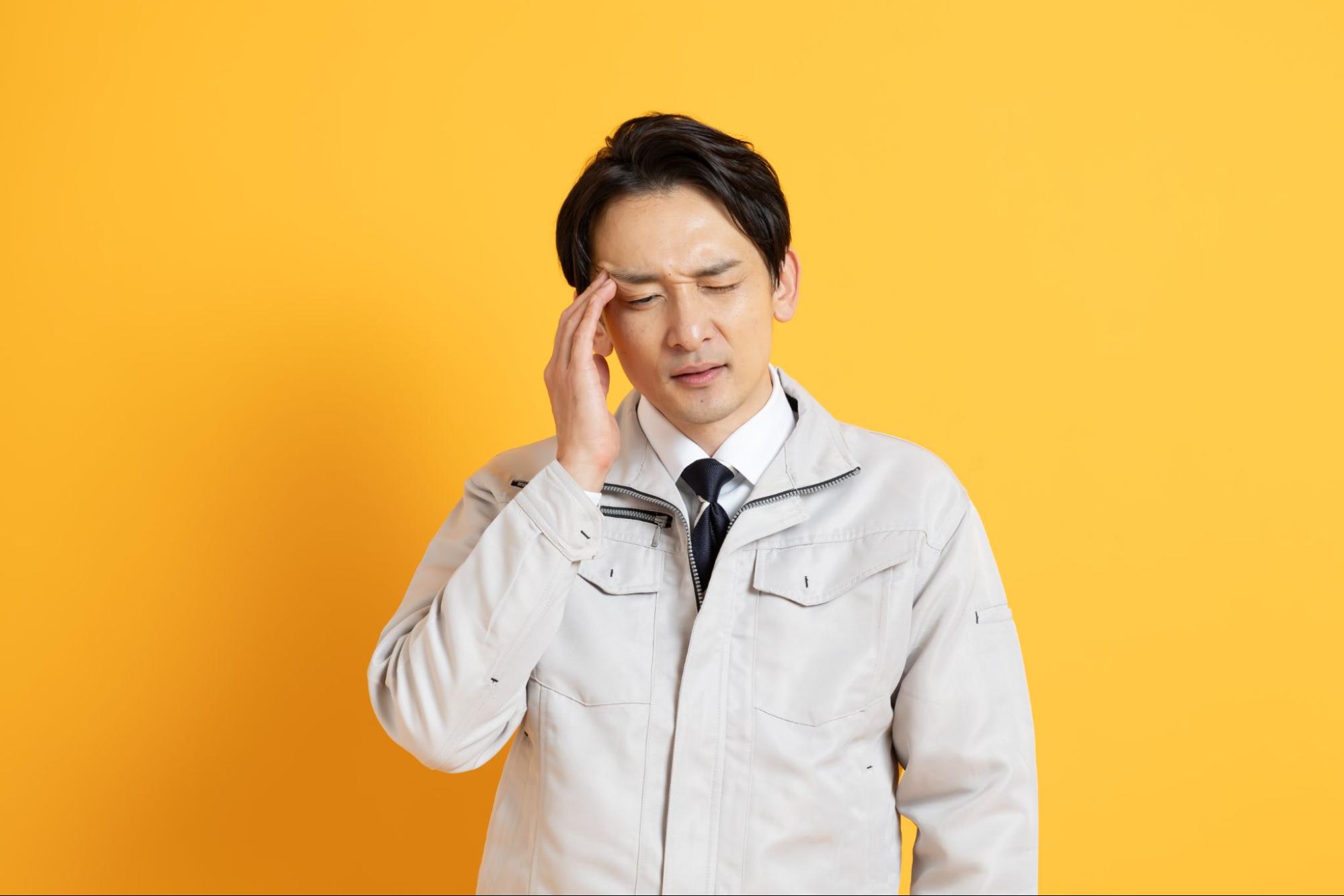
メーカーや製造業の仕事に向いていない人の特徴にはどのようなものがあるのか、ここでは以下の特徴を解説します。
- 体力に自信がない人
- 機械の扱いが苦手な人
体力に自信がない人
メーカーや製造業で勤務する場合、長時間立った状態での作業や重い物を運ぶ作業など体力が求められる場合があります。そのため、体力に自信のない人はよりケガのリスクが高まる可能性があるので、別の業種や職種への就職・転職を検討してみると良いでしょう。
機械の扱いが苦手な人
機械を扱うケースが多い点がメーカーや製造業の特徴です。機械の操作はマニュアル化されているケースが多いですが、複雑な操作を必要とする場面では機械の知識が豊富な人が重宝されます。反対に機械の扱いに苦手意識がある人は、トラブル対応などで適切な対処が難しくなるので、就職先や転職先を探す際は自分の得意・不得意を洗い出すようにしましょう。
製造業やメーカーは異なる部分があるものの、職種は同じものが多い

製造業とメーカーは、企業規模や作っている製品に違いがあります。しかし、営業や商品開発など職種については同じであるため、大まかな仕事内容は異なりません。どちらも未経験でも働けるほか、雇用が安定しているなどメリットが多いので、ものづくりやアイデアの構築が好きな人は、製造業やメーカーへの就職・転職を検討してみましょう。
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)