建設業の中でも専門性が高く責任の重い仕事として知られる「電気施工管理」。ネットでは「やめとけ」「激務」といった声も多く見られますが、すべての職場が過酷というわけではありません。
本記事では、電気施工管理がきついと言われる理由と、続ける価値がある理由、そしてホワイトな職場を見極めるポイントまで詳しく解説します。
電気施工管理が「やめとけ」と言われる理由

電気施工管理は社会に欠かせない重要な仕事でありながら、「やめとけ」と検索されることも少なくありません。ここでは、そう言われる背景を冷静に整理し、実際の現場で何が起きているのかを解説します。
長時間労働と人手不足で激務になりがち
電気施工管理の現場では、慢性的な人手不足が課題です。特に大規模工事や繁忙期には、職人や協力会社との調整に追われ、早朝から夜遅くまで働くケースもあります。現場の進行を止められないというプレッシャーから、休日出勤や残業が常態化してしまう企業も存在します。こうした労働環境が続くと、体力的にも精神的にも負担が大きく、「激務すぎて続かない」と感じる人が出てしまうのです。
責任の重さとプレッシャーが大きい
施工管理は、電気設備の安全性や品質を担う責任ある立場です。たとえば配線や受電設備に不具合があれば、建物全体の稼働に影響が及ぶこともあります。工程管理や予算、品質、安全の4大管理を同時にこなす必要があり、トラブルが起きた際は責任を問われることも。そのため「現場の責任が重くて精神的にきつい」と感じる人も少なくありません。
人間関係や職人気質の環境に疲れる
電気施工管理の現場では、ベテラン職人や協力会社との関係構築も重要です。現場によっては、職人気質の強い人が多く、言葉づかいやコミュニケーションの難しさを感じることもあります。特に若手や中途入社の社員は、上下関係の厳しさや独特の現場文化に戸惑うことがあります。人間関係のストレスが理由で転職を考えるケースも見られます。
給与が労力に見合わない現場もある
施工管理職は一見高収入に見えますが、長時間労働や休日出勤が多い企業では、時間単価で見ると割に合わないと感じる人もいます。特に下請け構造の中にある企業では、利益率が低く、給与面の改善が進みにくいことも。やりがいを感じても、待遇とのバランスが取れずに離職を考える人が増えています。
休みが取りづらくプライベートを犠牲にしがち
現場の工程がタイトな場合、会社によっては休日でも電話対応や急な呼び出しが発生することがあります。特に竣工前やトラブル対応時は休みが取りづらく、家族や友人との時間を犠牲にせざるを得ないことも。「ワークライフバランスが取りにくい」との声が多いのは、こうした背景があるためです。
電気施工管理を続ける価値がある理由
一方で、「きつい」と言われる環境の中にも、長期的なキャリアとして続ける価値がある理由が確かに存在します。
社会インフラを支える専門職としての安定性
電気施工管理は、建物や公共施設、インフラ設備に欠かせない存在です。景気の波を受けにくく、再開発やリニューアル工事など安定した需要があります。特に脱炭素社会の流れの中で、再生可能エネルギー設備やEVインフラなど新しい分野でも活躍の場が増えています。
国家資格によるキャリアの強み
「電気工事施工管理技士」は国家資格であり、資格を持つことで現場代理人や主任技術者としての地位を確立できます。資格は転職時の評価にも直結し、待遇アップにもつながります。また、経験を積めば建設業界全体で通用するスキルとなり、他業種への転職にも有利です。
現場経験が昇進や独立にも活きる
現場での管理経験は、将来的に会社の幹部や独立への道にもつながります。現場を知る人材はマネジメントや営業にも強く、独立して工事会社を立ち上げる人も多い職種です。経験を積むほど、キャリアの選択肢が広がるのも施工管理の魅力です。
技術革新で働き方が改善されつつある
近年はICT施工やBIM(Building Information Modeling)、ドローン測量などの導入により、現場業務の効率化が進んでいます。書類作成のデジタル化も進み、残業時間の削減やリモート管理が可能な企業も増えています。こうした技術革新により、「きつい仕事」から「スマートな管理職」へと変わりつつあります。
ホワイトな電気施工管理会社の見極め方

ネガティブな現場ばかりではありません。環境の整った企業を選べば、施工管理は安定して長く働ける仕事です。
残業時間・休日・離職率をチェックする
まずは求人票や口コミサイトで「月平均残業時間」「年間休日」「離職率」を確認しましょう。月40時間以内の残業・年間休日120日以上が目安です。これらを明示している企業は、労務管理がしっかりしている傾向があります。
教育体制や安全管理が整っているか確認する
新人研修や資格取得支援、安全衛生教育が整っている企業は、人材を大切にしている証拠です。特に安全管理に力を入れている現場は、事故が少なく、社員の定着率も高い傾向があります。
元請け案件が多くスケジュールに余裕がある
元請け企業や大手ゼネコン直下の案件が多い会社は、納期や予算の調整に余裕があります。下請け構造に比べ、無理な工期や突貫作業が少ないため、働きやすさに直結します。
口コミや求人情報で実態を把握する
企業のホームページだけでなく、転職サイトやSNSで社員の声をチェックすることも重要です。「現場の雰囲気」「上司との関係」「休日の取りやすさ」など、リアルな口コミが参考になります。
ブラック現場に陥りやすい環境の特徴

反対に、働きづらい環境を見抜く力も欠かせません。
下請け構造が複雑で納期に追われる
多重下請けの現場では、上位会社の指示が重なり、現場監督が過重なスケジュールを強いられることがあります。納期に追われて残業や休日出勤が当たり前になるケースも。
人員不足で一人あたりの負担が重い
現場監督が複数の現場を掛け持ちする会社は要注意です。安全確認や書類作成などの業務が集中し、ミスやトラブルのリスクも高まります。
管理体制が整っておらず安全意識が低い
ヘルメットの着用や安全ミーティングが形骸化している現場は、管理体制が機能していないサインです。こうした環境ではトラブル対応も属人的になり、疲弊しやすくなります。
電気施工管理で長く働くためのポイント
同じ施工管理でも、働く会社や現場次第で負担は大きく変わります。
自分に合った現場や会社を選ぶ
住宅・商業施設・プラントなど、現場の種類で求められるスキルや働き方は異なります。自分の得意分野や生活リズムに合う現場を選ぶことで、無理なく働き続けられます。
資格取得で役職・待遇アップを狙う
第二種電気工事士、第一種電気工事士、施工管理技士など、資格があると責任者としての立場や給与が上がります。企業によっては資格手当が月1〜3万円つく場合もあります。
チームワークや報連相を意識して円滑に働く
現場はチームで動くため、報連相(報告・連絡・相談)が重要です。関係者と信頼関係を築くことで、トラブルを未然に防ぎ、精神的な負担も減らせます。
働き方改革の進む企業を選ぶ
建設業でも「週休2日制」「DX化」「残業削減」を推進する企業が増えています。国交省の働き方改革モデル企業などを参考にするのも一案です。
やめとけではなく「見極め」が大事

ネット上で「やめとけ」と言われるのは、厳しい現場を経験した人の声が目立つためです。しかし、すべての職場が過酷というわけではありません。環境や経営方針によって、働きやすさは大きく変わります。「電気施工管理=きつい」と決めつけるのではなく、自分に合った会社を探すことがキャリアを長く続ける鍵です。労働環境を見極め、スキルアップを重ねれば、安定したキャリアを築くことができます。
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
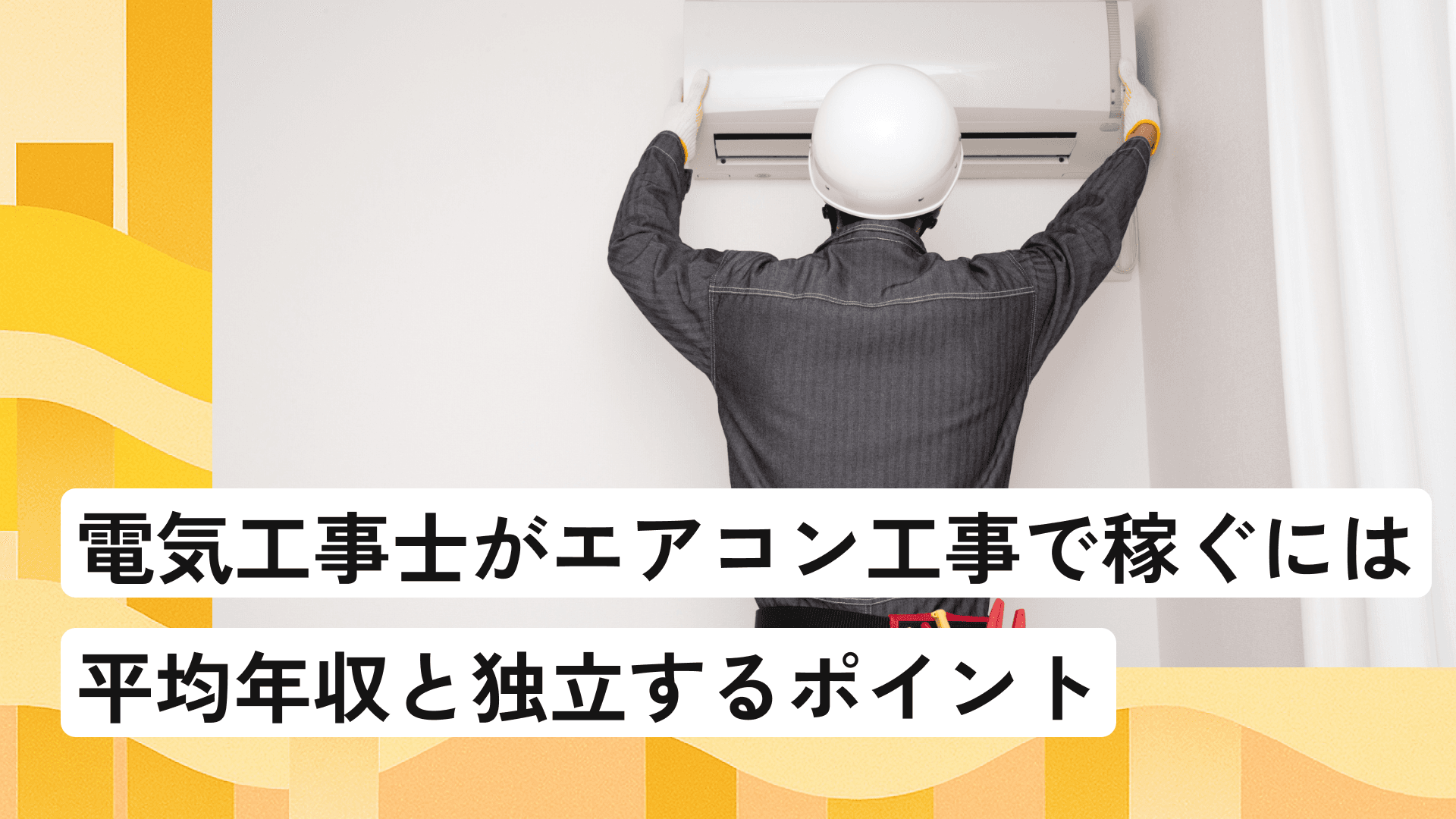
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)