電気工事は、私たちの生活や産業を支える欠かせない仕事です。住宅から工場、公共施設まで、あらゆる場所で電気を安全に使えるようにするための専門職といえます。この記事では、電気工事の種類や資格、現場ごとの仕事内容、将来性まで幅広く解説します。
電気工事とはどんな仕事か

電気工事とは、電気を安全かつ安定的に供給するための設備を設置・点検・修理する仕事です。家庭用から産業用まで幅広く、建築やインフラ整備においても重要な役割を担っています。
電気工事の基本的な役割と重要性
電気工事士は、電気が正しく流れるよう配線や機器の設置を行い、火災や感電などの事故を防ぐ使命を持っています。電気は目に見えないエネルギーであるため、施工の安全性と精度が極めて重要です。
たとえば、コンセントや照明を設置する住宅工事から、工場の大型設備やビル全体の配線管理まで、すべて電気工事士の手で整備されています。つまり、社会の「電気インフラ」を支える縁の下の力持ちなのです。
現場で行われる主な作業内容
主な作業には、配線工事、照明・コンセント設置、分電盤の取り付け、電気機器の接続・調整などがあります。新築時の施工だけでなく、リフォームや老朽化に伴う修繕、定期点検も大切な業務です。
また、施工図を読み取り、配線ルートを設計する「図面理解力」も求められます。現場では他の職人や建築士と協力して作業することも多く、チームワークも欠かせません。
一般電気工作物と自家用電気工作物の違い
電気工事には「一般電気工作物」と「自家用電気工作物」の2種類があります。
前者は住宅や商店など600V以下の電圧を扱う工事で、第二種電気工事士が担当します。一方、後者は工場やビルなど高圧電力を扱う設備を指し、第一種電気工事士や電気主任技術者が対応します。つまり、電圧や用途によって求められる資格や責任の範囲が異なるのです。
電気工事の主な種類
電気工事と一口に言っても、現場や目的によって多様な種類に分かれています。それぞれの分野で必要な技術や知識も異なります。
屋内配線工事(住宅・店舗など)
住宅やオフィス、店舗などの屋内で、照明・コンセント・エアコン・分電盤などを設置する工事です。図面に基づき、壁や天井裏にケーブルを通して配線します。仕上がりの美しさや使い勝手も求められるため、丁寧な作業が重要です。
屋外配線工事(電柱・外灯など)
道路や公園など屋外での配線工事を指します。電柱間の配線、街灯の設置、防犯灯や信号機の電源供給などが含まれます。高所作業車を使うこともあり、安全管理が非常に重要です。屋内よりも体力を必要とする現場ですが、公共性の高い仕事としてやりがいがあります。
電気通信・弱電工事(LAN・防犯カメラなど)
LAN配線、インターホン、防犯カメラ、放送設備などを設置する工事です。電力を扱う「強電」に対し、通信や制御信号を扱う「弱電」と呼ばれます。IT化やIoTの普及に伴い、需要が急増している分野です。
消防設備工事(火災報知器など)
火災報知器やスプリンクラー、非常放送などの設備を設置・点検する仕事です。消防法に基づく資格が必要で、定期点検や報告も義務づけられています。人命を守る重要な分野であり、社会的使命感を持って働ける仕事です。
太陽光・再生可能エネルギー関連工事
太陽光発電や蓄電池、EV充電設備などの施工を行います。地球環境への関心が高まる中、再生可能エネルギー分野は今後も拡大が見込まれます。最新技術を取り入れた施工やメンテナンススキルが求められる、成長分野の一つです。
電気工事に必要な資格の種類

安全かつ法的に電気工事を行うには、国家資格が必要です。特に「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」は基本資格として知られています。
第一種電気工事士と第二種電気工事士の違い
第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600V以下の工事が可能で、初心者が最初に目指す資格です。
一方、第一種電気工事士は工場・ビルなどの高圧電気を扱う現場にも対応でき、業務範囲が広がります。キャリアアップや独立を目指すなら、第一種の取得が有利です。
工事担任者や電験三種などの上位資格
通信系の「工事担任者」や、高圧電気設備の保守管理を行う「第三種電気主任技術者(電験三種)」など、上位資格を取ることでさらに専門性が高まります。特に電験三種は難関資格ですが、取得すれば大規模施設や発電所などでも活躍の場が広がります。
資格取得までの流れと勉強方法のポイント
まずは第二種電気工事士から挑戦するのが一般的です。試験は筆記と技能に分かれており、電気理論や配線図、器具結線などの実践知識が問われます。
独学でも合格可能ですが、通信講座や実技講習を併用することで理解が深まります。資格を取れば現場の信頼度も高まり、就職・転職に大きく有利です。
現場別に見る電気工事の仕事内容
現場の種類によって作業内容や求められるスキルは大きく異なります。自分に合った環境を選ぶことが長く続ける秘訣です。
住宅・マンションでの工事内容
主に新築やリフォーム時に、照明やコンセント、インターホンなどの配線を行います。住む人の快適さを左右するため、デザイン性や安全性を両立させる技術が求められます。お客様とのやりとりが発生する現場も多く、コミュニケーション能力も重要です。
工場・ビル・商業施設での工事内容
高圧電力を扱う大型設備や動力盤、空調・照明システムなどの施工・保守を担当します。図面作成、電気負荷の計算、安全確認など、より高度な知識が必要です。プロジェクト単位での仕事が多く、第一種電気工事士の資格が生かされます。
公共施設やインフラ関連の仕事
トンネル照明、信号機、鉄道・空港施設など、公共インフラを支える工事も重要な分野です。社会への貢献度が高く、長期的な案件が多いため安定性があります。安全管理体制も厳格で、国家資格保持者の活躍が求められます。
電気工事の将来性とキャリアパス

電気工事の需要は今後も拡大が見込まれています。特に再生可能エネルギーやスマートホームの普及が後押ししています。
再生可能エネルギーやIoT時代に広がる需要
太陽光発電、蓄電システム、EV充電など、電気の活用範囲は急速に広がっています。また、IoT家電やスマートシティの整備に伴い、通信・制御系の工事も増加中です。技術革新が続く中で、電気工事士は時代に必要とされる存在です。
資格取得で年収アップ・独立も可能
資格を取得し経験を積むことで、施工管理者や責任技術者への昇進、さらには独立開業も可能です。平均年収は400〜600万円ですが、第一種取得者や独立事業主では年収700万円以上も目指せます。資格がそのまま収入と信頼に直結する職種です。
出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(jobtag)」、doda職種図鑑、求人ボックス「電気工事士の仕事の年収・時給」
未経験から目指す場合のステップ
未経験者はまず現場でアシスタントとして働きながら、第二種電気工事士の資格取得を目指すのが一般的です。実務経験を積むことで、より高度な資格や現場管理職にもステップアップできます。実践と学習を両立できる職種のため、手に職をつけたい人にもおすすめです。
自分に合った電気工事の分野を見極めよう
電気工事は、住宅から公共施設、再エネ分野まで多岐にわたります。自分の得意分野や興味に合わせて、屋内・屋外・弱電などの分野を選ぶことがキャリア形成の第一歩です。
電気工事士は資格が命ともいえる職業です。第二種から始めて第一種や電験三種へとステップアップすることで、将来の選択肢が広がります。確かな技術を身につけ、社会に貢献できる職人を目指しましょう。
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
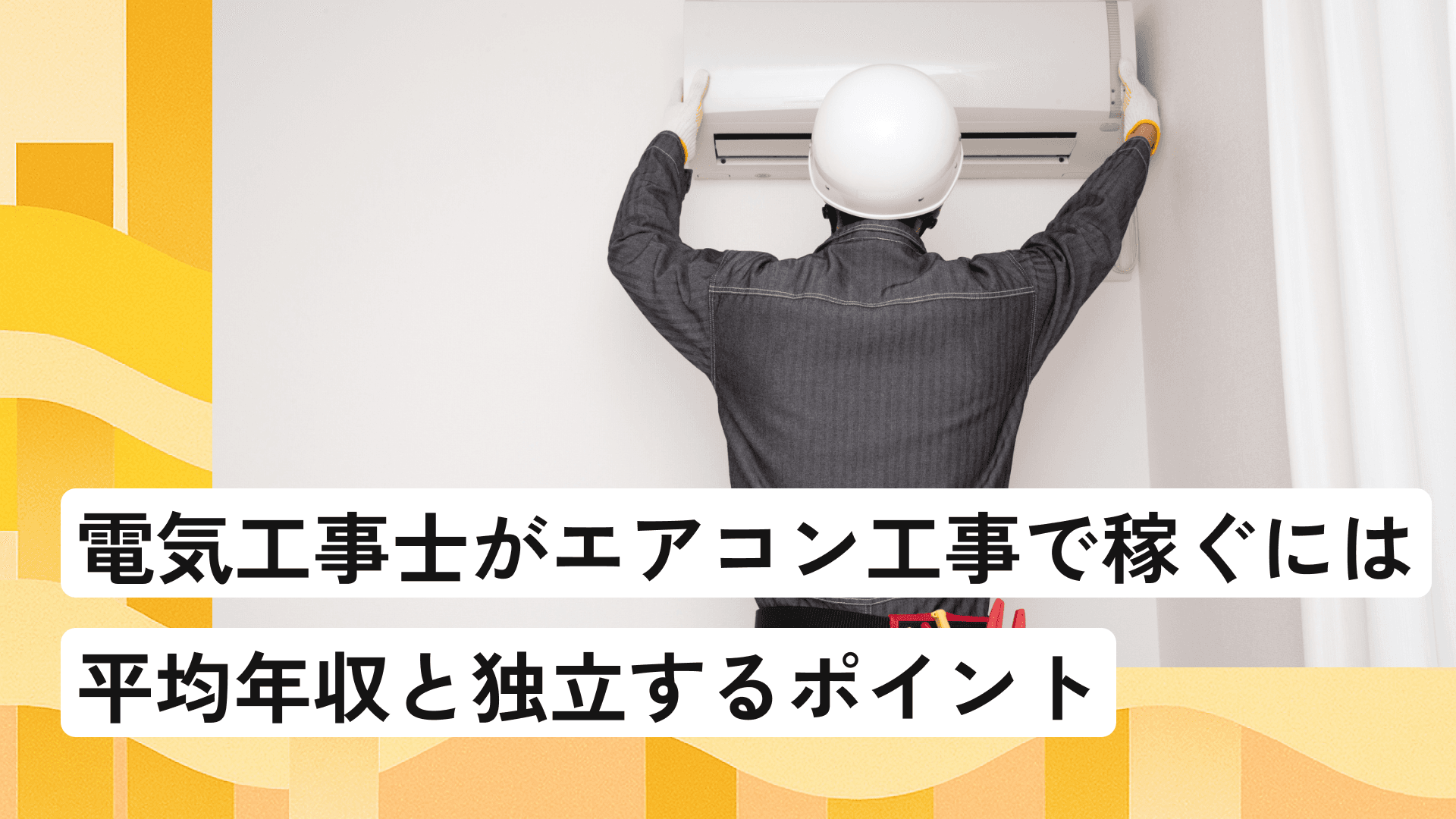
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)