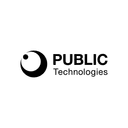株式会社パブリックテクノロジーズ(以下「パブリックテクノロジーズ」)は、「暮らし続けたいまちをつくる」というミッションのもと、GovTech(※1)事業の運営を通して地方自治体のパートナーとして地方課題の解決に取り組んでいるスタートアップ企業です。
代表取締役の杉原は学生時代に起業し、Bリーグの立ち上げや電動キックボード事業の運営などに携わり、常に挑戦を続けてきました。その経験と洞察力を活かし、パブリックテクノロジーズは地方自治体と密接に連携し、テクノロジーを活用した革新的なサービスを提供しています。
今回は杉原の半生を紐解きながら彼が描いてきた挑戦の軌跡とともに、地方に新たな価値を創出するパブリックテクノロジーズの魅力についてお伝えします。
※1=GovTech(ガブテック):「行政・政府(Government)」と「技術(Technology)」を掛け合わせた言葉。コンピュータやAIなどのデジタル技術を用いて、行政サービスの向上や行政課題の解決を図ることを意味する。
枝葉から根幹へー異色のキャリアと学生起業を経て感じた社会課題
――杉原さんが社会課題に目を向けた原点は?
原点は大学時代にBリーグの立ち上げに携わったことです。当時のプロバスケットボール界は、トップリーグの分裂に伴う日本代表の国際資格停止処分や選手・リーグの認知度不足など様々な課題を抱えていました。私は大学生でしたが、広報担当のインターンの立場で、どうすればリーグを盛り上げ、地域に根付かせることができるのかを立案していました。初めての仕事はリーグのロゴデザインの最終案に対して中学生・高校生から意見を貰う事でした。メディア露出を増やすための戦略を実行する中で、Bリーグが及ぼす地域社会への影響力を実感し「地域に特化した社会課題を解決したい」という強い想いが芽生えたんです。
――Bリーグの立ち上げから、なぜ公共ライドシェア事業に挑戦しようと思われたのですか?
Bリーグ運営での経験を通して、社会課題の解決には既存の枠にとらわれない発想と行動力が必要だと痛感しました。そんなとき大学時代の同級生から「電動キックボード事業で起業しよう」と話を持ちかけられたんです。当時、電動キックボードは新しいモビリティとして注目を集めていましたが、法整備が追いついておらず、安全面や利用ルールなど、多くの課題を抱えていました。まさに「混沌」とした状況でしたが、だからこそ新しいルールを創り、社会実装していくことに大きなやりがいを感じたんです。関係省庁との交渉や、業界団体との連携を通じて、法改正に間近で関われたことは大きな自信につながりました。
――現在は地方自治体のパートナーとして地方創生事業を手がけていますが、その想いをお聞かせください。
電動キックボード事業を通して、地方の交通インフラの脆弱さを痛感すると同時に、電動キックボードだけでは解決できないより根本的な課題が存在することに気づいたのです。「電動キックボードだけでなく、根源である「交通」に対してアプローチできることはないだろうか?」と自問自答するようになりました。電動キックボードはあくまでも既存の交通網を補完する、いわば枝葉の部分。電車やバスといった公共交通機関が十分に機能していない地域では、真の意味での移動の自由を確保することは難しく、そのような地域のために何ができるのか?この問いが、現在の事業へと繋がる大きな一歩でした。
現在の共同代表である青木とは、この事業を構想し始めた頃に出会ったんです。同じシェアオフィスを利用していてお互いの存在は知っている程度でしたが、ある日彼が地方自治体向けのモビリティ関連事業を手がけていることを知り、意気投合。「一緒に事業を展開したらより大きなインパクトを生み出せる」と確信し会社を統合して現在のパブリックテクノロジーズになりました。
ro.jpg)
「暮らし続けたいまち」を実現するー過疎地での挑戦が拓いた事業の礎
――パブリックテクノロジーズはどのように「暮らし続けたいまち」を実現していくのでしょうか?事業内容について教えてください。
私たちは「暮らし続けたいまち」の実現に向け、住民の方々に向けたサービスと同時に、行政職員の方々へのサポートという2つの軸で事業を展開しています。
住民の方々向けには、テクノロジーを活用した利便性の高い交通サービスを提供しています。現状の交通状況の分析から最適な交通網の設計、システムの導入・運用まで一貫してサポートし、過疎化や高齢化が進む地域でも誰もが自由に移動できる環境を整備します。具体的にはバスや鉄道の運行データと住民の実際の移動経路のニーズを分析し、不要な路線の廃止や運行時間の調整などを提案します。その上で、地域住民のニーズに合わせたオンデマンド交通サービスやライドシェアといった新しい交通手段を導入することで、より効率的で利便性の高い交通システムを実現するといった流れです。
一方で行政職員の方々へのサポートとしては、生成AIを活用した業務効率化ツールを提供しています。地方自治体は職員の減少や業務の複雑化といった課題が深刻化しているため、限られたリソースでより多くの業務をこなせるよう支援しています。
――初期から「人口減少」や「過疎化」などに課題のある自治体にフォーカスしていたのはなぜでしょうか?
最も深刻な課題を抱え、私たちのサービスが最も必要とされている場所だと考えているからです。
最初に支援を開始したのは、茨城県の行方市でした。人口3万人ほどのこの市は、10年以上前に鹿島鉄道が撤退し電車が存在していません。バス路線も広大な面積と人口減少のギャップにより、非効率な運行を強いられていました。
行方市のように公共交通の維持が困難な自治体は少なくありません。私たちが首都圏ではなく地方にフォーカスしたのは、こうした課題に真正面から向き合い、解決策を提供することで、「暮らし続けたいまち」の実現に貢献できると考えたからです。行方市での経験は私たちの事業展開の礎となっています。
――公共交通の最適化に取り組む企業は他にも存在しますが、パブリックテクノロジーズの競争優位性はどこにあるのでしょうか?
公共交通の最適化に取り組む企業は存在しますが、首都圏に集中しており多くの利用者に活用してもらうことを目指しているケースが多いです。地方に特化し、住民向けサービスと行政向けサービスの両輪で事業を展開している企業は少ないのではないでしょうか。
ビジネスモデルとしては自治体から予算をいただくため、住民の利用率が低くても収益に影響が出ないという構造的な問題を抱えているのも現実です。結果として「導入したものの、全く使われていない」となれば意味がありません。
私たちは地方自治体に特化したサービス提供と、住民と行政の双方に寄り添ったサービス開発を強みとしています。また交通サービスだけでなく、健康管理や防災情報の発信といった地域住民が必要とする機能をアプリ(※2)に搭載することで、地域社会全体のコミュニティ活性化に貢献することを目指しています。
※2:パブリックテクノロジーズが開発したアプリ「パブテク」は、自治体業務を効率化し住民の生活をより便利にするためのさまざまな機能を集約し管理している。具体的には、公共ライドシェア/オンデマンド交通/AIチャットボット/地域通貨/住民アンケートなど。
ro.jpg)
社会課題に真剣に向き合いたいー急成長のスタートアップで、社会を動かすダイナミズムを体感する
――代表の杉原さんが思う、パブリックテクノロジーズで働く魅力とは?
一言で言えば社会貢献度の高さです。「暮らし続けたいまちをつくる」ことへの共感が、働く上での大きなモチベーションとなっています。資本主義の枠組みの中で成長していくことは大前提ですが、同時に高い公共性を持ち、課題を抱えている地方自治体に直接貢献できるのが、大きな魅力だと思います。
実際、社員の中には地方出身者や元公務員の方も多く「社会課題に向き合いたい」という想いを胸に秘めている人が集まっていると感じています。強い使命感を持つメンバーと共に働くことで、互いに刺激し合い高め合いながら成長できる環境です。
――国の方針や政治と密接に関わる事業であるからこそ、難しさや苦労もあるのではないでしょうか?
そうですね。常に外的環境にもアンテナを張り、社会情勢の変化を敏感に察知する必要があります。制度改正や補助金制度の変更など、私たちの事業に大きな影響を与える出来事が日々起こり、時には予期せぬ事態が発生し、迅速な対応を迫られることもあります。関係省庁との調整や、自治体との交渉など困難な局面に直面することも少なくありません。
しかし、これは同時に大きなチャンスでもあります。例えばライドシェアの制度改正は、私たちにとって大きな追い風となりました。いち早くこの変化に対応しサービスを拡充することで、多くの自治体から支持を得ることができたのです。社会の変化をいち早く捉え、予測とそれに対する仕込みをしておくことで、新たな事業機会を創出することができるのではないでしょうか。
「冠婚葬祭に全部出たいと思えるか」ーユニークな採用基準から見える「人」の価値
――人材採用においてはどのようなことを重視していますか?
スキルや経験ももちろん重要ですが、何よりも「人柄」を重視しています。私たちが採用基準として掲げているのは「冠婚葬祭に全部出たいと思える人かどうか」です。少しユニークな表現かもしれませんが、一緒に働く仲間として、そして人として、心から信頼できるかどうかを判断するための重要な指標だと考えています。
具体的には、素直さ・誠実さ・責任感・そして真摯に仕事に取り組む姿勢を持った人材です。開発職に関してはスキル水準の選考はありますが、カルチャーフィットも重要な判断基準です。開発職以外の職種では、ほぼカルチャーフィットに重きを置いています。私たちの事業は、経験値や年齢は関係ありません。柔軟な思考と高いキャッチアップ力、そして、自治体と接する上でのコミュニケーション力が求められる領域です。社会課題に真摯に向き合い、課題の本質を見抜いて解決したいという想いを秘めているメンバーとこれからも一緒に働いていきたいです。
ro.jpg)
%2520(1).jpg&w=3840&q=75)